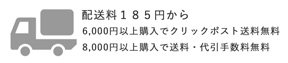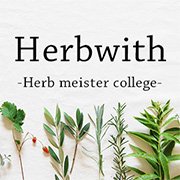HMCフィトテラピー通信 〜肺・呼吸器ケア〜
 Date:2025.9.25
Date:2025.9.25Category:ハーブレッスン
Writer:佐藤

HMCフィトテラピー通信では、こころとからだにまつわるテーマを毎月設け、ハーブや精油を用いた日々のケアや過ごし方についてお伝えしていきます。
暮らしの中にフィトテラピーを取り入れて、植物のある暮らしをより多くの方に愛しんでいただけるようご提案していきます。
********
蒸し暑い夏が終わりホッとしたのも束の間、秋の空気は澄んでいてとても心地よい一方で、気温や湿度の変化が呼吸器系に負担をかけやすい季節を迎えました。
乾燥した空気は鼻や喉の粘膜を乾かし、大切なバリア機能を低下させます。
その結果、異物やウイルスが体内に入り込みやすくなり、喉の痛みや咳などといった不調につながります。
そこで大切なのが肺や呼吸器を「潤す」ということ。肌の潤いと共に、呼吸器にも保湿ケアが必要です。
年々夏の暑さは厳しくなっています。強い日差しと熱気は身体の水分を奪い乾燥を招きます。
意識的に潤いを補うセルフケアをして秋に備えましょう。
呼吸器とは「鼻」「咽頭」「喉頭」「器官」「気管支」「肺」の器官からなり、呼吸により酸素を取り入れ二酸化炭素を排出するという空気の交換をする働きを担っています。
また、上気道(鼻腔、咽頭、喉頭)から下気道(気管、気管支、細気管支)にあたる気道の役目は、空気の通り道として肺への酸素の取り込みと二酸化炭素の排出だけでなく、異物が肺に入らないように潤いのベールとして働いています。
外の空気が身体に合った温度になるように温められ、適度な湿り気をまとい、微細な埃やウイルスは粘膜や繊毛で絡めとられ奥まで入らないように排出することで肺は守られています。
特に秋は空気が乾燥し、気道がまとう潤いのベールが薄くなり防御の力が弱まってしまいます。
喉がイガイガする、空咳が続く、風邪を引きやすいなどの症状を感じる方も多いのでは。
これは気道の粘膜が乾燥して外敵から守るバリア機能が弱まっているサイン。
呼吸器系の持つ、吸い込んだ空気を加湿・加温しながら肺へ届ける仕組みは乾燥が大敵。
だからこそ、気道をただの空気の通り道としてではなく、肺を守る潤いの器官として労わることが、これからの乾燥の季節を健やかに過ごすカギとなるのです。
<おすすめハーブティー>
『タイム』
ちょっと喉にきちゃったかも。というときに常備しておくと心強いタイム。
シングルだと飲みづらいなというときは、エルダーフラワーやカモミールなどまろやかなハーブとブレンドすると飲みやすくなります。
濃く煮出せばうがい薬にもなりますよ。
『イガイガ・ガラガラGood-bye〜Throat care〜』
喉の粘膜を潤して守ってくれるブレンド。
声の仕事をされているお客様にもご愛飲いただいている隠れた名品です。
異物を外に出す働きをする繊毛や粘膜は充分な潤いがあってこそ力を発揮します。
鼻や口、皮膚は乾いた空気を最初に受け止める場所になります。
乾燥する季節の外出時はマスクをして、更に内側に薄いガーゼなどを当てると保湿力がアップします。
また、タンブラーでハーブティーなどの温かい飲み物を持ち歩き、こまめに喉を潤しましょう。蒸気を吸い込むことも保湿になりますね。
家の中では加湿器や濡れタオルを干す、または洗濯物の室内干しで部屋の湿度を40〜60%に保ちましょう。
観葉植物の蒸散作用も室内の加湿に役立ちます。
加湿のしすぎはカビの原因となるので、湿度はどんどん上げるよりも程よい状態でキープすることが大切です。
更に、質の良い睡眠を取ることで「陰液」と呼ばれる水分がしっかり育まれ体内を巡り肌や粘膜を潤すと考えられています。
睡眠不足が続くと肌や目の渇きが気になることありませんか。
夜は身体を休めて陰を養う大切な時間。特に秋冬は乾燥を防ぐためにも良質な睡眠で体内の保湿力を保つことが必要です。
<おすすめハーブティー>
『Good night』
寝たい時間の1時間くらい前に飲むのがおすすめです。
できればスマホタイムは終了し、ゆったりと眠る準備をはじめるとよいでしょう。
東洋医学でいう「肺」の働きの一つに、呼吸によってキレイな空気を体内に取り込み、脾で作られた栄養を各臓腑に運んで、汚れた空気を吐き出すというものがあります。
次に水分代謝の調整や管理も担っており、それにより肌や粘膜を瑞々しく保ち喉や鼻が潤って快適に過ごせるように調整しています。逆に肺の潤いが不足すると空咳や肌のかさつきが出てきます。
特に秋は肺の働きが亢進するため、負担がかかりやすい季節。肺は鼻や喉、気管を通じて直接外界と接するため邪気に侵入されやすくデリケートな臓腑であり、滋潤と温かさを好む特徴があるため、乾燥の邪気「燥邪」を避け、適度に温めながら過ごすことがポイントとなります。
まずは深い呼吸で気を巡らせましょう。
この数分の深呼吸が肺の気の流れを整えます。呼吸が浅くなる猫背や巻き肩にならないように意識することも大切です。
適度な有酸素運動も肺の働きが高まり潤いも全身に行き渡りやすくなります。ウォーキングなど無理なく続けられる運動を日常にとりいれましょう。
また、五臓にはそれぞれに関わる感情もあります。肺は「悲しみ」と関わる臓とされています。太陽が照りつける夏から一転、秋になり植物が枯れ落葉する様子は物悲しさを感じ沈み込みがちになることも。
気候が良く旅にも最適な季節と捉えて、行楽や味覚を楽しむことも肺の養生に繋がります。
呼吸器系に関係の深い臓腑「肺」についての詳細は、HMCのオンライン講座「陰陽五行フィトテラピー講座」で詳しく説明していますのでご興味のある方はこちらをご覧ください。
フィトテラピーでは肺・呼吸器ケアに関してどのようなサポートできるでしょうか。
「食べ物」「香り」「ハーブティー」の観点からおすすめしていきます。
<食べ物>
肌にクリームを塗ることやマスクを使うことなどの外側からのケアができたら、乾燥から身を守るため内側からもケアをしましょう。内側からのケアは身体を潤す食材を摂ること。
季節にはそれぞれ五味五色の概念があります。秋の色は「白」。白い食べ物は肺を潤す効果があるとされています。
白ごま、カブやレンコン、梨、ゆり根も白いですね。おすすめなのは「白きくらげ」。食べる美容液なんて言われるほど潤します。乾燥した白きくらげは手に入りやすいので、秋の気配を感じる頃に準備しておくと良いですね。鍋料理の具材として、または酢の物などで気軽に取り入れましょう。
また、ビタミンAを多く含む食材を意識して摂りましょう。網膜や皮膚、そして鼻や喉、気管支や胃腸の粘膜の健康維持に不可欠な栄養素です。
動物性ではレバーや鰻、卵黄などに含まれます。すぐにビタミンAとして使える栄養素ですが、肝臓に蓄積しやすいため食べ過ぎには注意が必要です。
植物性ではビタミンAの前駆体であるプロビタミンAが緑黄色野菜に多く含まれ、その中でも効率よく必要に応じてビタミンAに変換されるβカロテンは人参やかぼちゃ、ほうれん草、春菊など色の濃い野菜に多く含まれます。これらは秋に旬を迎える野菜でもあります。旬の野菜を楽しみながら潤いの養生ができますね。
粘膜が元気であることは病原体の侵入を最前線で防ぐ体勢が整うということ。
バランスの取れた食生活を心掛け身体の渇きを内側から癒しましょう。
<香り>
肺や呼吸器ケアのためのおすすめの精油は『ユーカリ』です。
特にユーカリグロブルスは去痰作用や呼吸器系への働きが強く、風邪の季節に持っておきたい精油。鼻通りも良くなります。
マグカップにお湯をいれて、そこに一滴ユーカリの精油を垂らして、目をつぶって蒸気を吸い込むやり方もおすすめ。
1.8シネオールという成分が多く含まれますので、お子様への使用や長時間の使用にはご注意ください。ディフューザーでの使用は一回につき20分くらいまでにとどめておきましょう。
<ハーブティー>
■シングルハーブ
『マローブルー』
鮮やかなブルーが浸出する人気のハーブ。レモン汁を数滴垂らしてピンク色に変化する様子を楽しんだことがある方もいらっしゃるのでは。少しとろみを感じる浸出液は喉や気管支の炎症に役立ち、症状を落ち着けます。
『リコリス』
砂糖の50倍の甘さを持つと言われているリコリス。潤しながら炎症を抑える作用があるため、喉が乾燥した時のイガイガを鎮めてくれます。メディカルハーブ1に相当し、薬理効果が高いぶん禁忌もあります。詳しい禁忌は商品ページをご確認ください。
■ブレンドハーブ
『ずるずる・たらーりGood-bye〜Allergy care〜』
タイムとペパーミントが爽快なブレンドです。ペパーミントも喉の炎症による痛みが気になる時に役立ちます。鼻がずるずるする時は冷えているサインかもしれません。オレンジピールで温めてゆったりリラックスしましょう。
『浄化』
体調を崩しやすい季節の変わり目にぴったりのブレンドです。また、人混みにもまれてなんだか浄化したい気分の時や、忙しすぎて自分のケアができていないな、と感じる時にも。エキナセアがブレンドされ、免疫を賦活してくれます。
※この商品は微量のカフェインを含みます。
まだまだ厳しい暑さは残っているのに、立秋を過ぎたころから粘膜(特に鼻と喉)の乾燥が気になり始めました。
そんな些細なことで秋の気配を感じていますが、その他のバロメーターとして目安にしているのが牛乳です。
夏は購入意欲がないのですが、暑さの中にも少し風が涼しかったかも、などと思い始めたころに必ずミルクティーが飲みたくなるのです。乳製品は身体を潤す食材。そして紅茶は身体を温めてくれる飲み物。スーパーで牛乳を手に取った瞬間から、そろそろ秋の準備を始めようと思うのでした。
皆さんもご自身なりの季節を感じ取るセンサーを敏感にして、次の季節を迎える準備をしてくださいね。